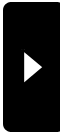2010年03月11日
山の地形用語。
山の地図を眺めていると、、、
面白い地名を見つけたり、、、
違った山域なのに同じ地名が存在していたりする。
そういったものは地形の様子から地名になったものが多い気がする。
山の地形などはカタカナ表記のものも多く、、、
語源が日本語なのか英語なのかフランス語なのかドイツ語なのか、、、
山に登り始めた時は、何が何だか良く分からなかった。
山に登り始めてそれなりに時間が経ち、
なじみのある、なんとなく意味が分かる地形用語も増えてきたが、、、
一度、ちゃんと?調べてみようと思ってコツコツと探し貯めていた。
主に地形に関する用語で、語源が日本語のものを集めてみた。
ただ、興味がある単語も調べたので、、、
ちょっとカテゴリー違いのものもあるかも知れない。
数週間に渡り、、、
仕事中の空き時間にチョコチョコ調べたものなので、
参考にしたサイトがドコであったかは憶えていないが、
一番、参考にしたのは【山どんの資料室】である。
■峠
まぁ、ぶっちゃけると調べることもないかも知れない。
しかし、山にはこの単語と似た意味の言葉が多いので、
まず、これから始める。
---------------------------------------------------------------------------
昔から人々の生活に関わってきた山越えの道が通る鞍部、
または道が乗り越している尾根上を峠と呼ぶ。
峠は「交易路」があることが条件である。
---------------------------------------------------------------------------
ふむ。想像通りなのだ。
しかし、こんな言葉もあったな、、、
■乗越
---------------------------------------------------------------------------
峰と峰の低い部分(鞍部、コル)で、
古くからの交易路はないが、信仰のための人や猟師、登山者が通るところ。
交易路のある鞍部は「峠」。
---------------------------------------------------------------------------
ほぉ。峠という言葉は生活道にしか適応されないってことか。
ちなみにコルは英語で鞍部という意味だ。
■ダワ、タワ、タオ
至る所、山域に“大ダワ”という地名がある。
地形的想像はつくが気になっていた。
---------------------------------------------------------------------------
尾根のたわんだ所、鞍部を指す古語。
「乢」、「屹」、「嵶」、「垰」などの字を当てる。
---------------------------------------------------------------------------
む。鞍部の古語だったのか。
峠から始まった鞍部シリーズは、まだまだ続く。
■ダルミ、ノタル
奥秩父縦走路の飛龍山の近くに“北天ノタル”があり、、、
縦走路を雲取山の方まで進むと“三条ダルミ”がある。
どぉ違うのかと思っていたら同じような意味らしい。
---------------------------------------------------------------------------
ダルミ(だるみ)は垂れているという意味で、山の稜線が垂れていることを示す。
似たような地名にノタル、「タル」とは中くぼみの地形を示し、
両者とも山の鞍部を指す。
---------------------------------------------------------------------------
ああ。もっと激しい鞍部があったな。
■キレット
---------------------------------------------------------------------------
鋭く切れ込んだ急峻な鞍部。
カタカナでかかれることが多いが「切戸」と書く純粋な日本語。
長野県側で使われていた方言が一般化、地名化した。
富山県側では「窓」と呼ばれている。
---------------------------------------------------------------------------
キレットと言われると、やはり恐怖感が先に来る。
これからは「ちょっと急な鞍部。」と呼ぼうかな。。。
鞍部シリーズは終わり、次はピークシリーズだ。
■~丸
初めて丹沢の地図を見たときに“~丸”という山名が多くてビックリした。
---------------------------------------------------------------------------
峰、森、岳などと同じように、山を指す言葉のひとつ。
古代朝鮮語を起源とする説、丸い山容を起源とする説などがある。
関東周辺と四国が多い。
---------------------------------------------------------------------------
ふむ。
“~丸”も確かにヘンだなぁと思ったが、、、
四国の“~森”も違和感があったな。そういえば。
■ドッケ
奥多摩に多い山名だ。
私が好きな山で“三ツドッケ(天目山)”がある。
同じ長沢背稜に“芋ノ木ドッケ”という山もある。
---------------------------------------------------------------------------
「突起」がなまった言葉で尖った地形に付けられた名前。
三ツ峠山は三つの峰を意味する三ツドッケの転訛説も有る。
---------------------------------------------------------------------------
あらら。そうでしたか。
■頭
コレも各地にあるな。
---------------------------------------------------------------------------
尾根上にある突起した地形。
小さい峰の名前として使われることが多い。
---------------------------------------------------------------------------
身体の一部繋がりで次に飛ぶ。
■肩
北岳にもあるし、川苔山にもある地名だ。
---------------------------------------------------------------------------
山頂を人の顔に見立てて、山頂の直下にある尾根の平坦部。
---------------------------------------------------------------------------
今度は動物の身体にジャンプする。
■馬の背
この地名も多い。
南アにもあるし丹沢にもある。
馬の背のように平坦な所のことかと思っていたが違った。
---------------------------------------------------------------------------
両側が切り落ちた谷、崖になっているような狭い尾根のこと。
---------------------------------------------------------------------------
そっか。
そういえば、そんな所につけられている地名だな。
動物シリーズに変わる。
■馬返し、駒止
---------------------------------------------------------------------------
昔、馬から降りて徒歩で歩き始めた場所の地名。昔(から)の登山口。
山岳信仰においては、これより神聖な場所で牛馬をいれない地点。
そのほか、急斜であったり、道が細かったりで、これ以上は馬が登れない地点。
---------------------------------------------------------------------------
なんとなく予想通りだ。
けど、大倉尾根の“駒止”はアソコまでにも急な所があるけどなぁ。
乗馬が上手ければ行けるのかな??
■牛首
---------------------------------------------------------------------------
牛の首のようにくびれた尾根。
または、そう見える場所。那須岳の牛首などが有名。
---------------------------------------------------------------------------
乾徳山の近くにもあったような。
以降は取りとめも無く進める。
■ゴーロ
コレは地形の状態を示す言葉だと思っていたが、
意外な山名の由来になっていたので載せる。
---------------------------------------------------------------------------
大きな岩がゴロゴロしているところ。広さには関係しない。
カタカナ表記が多いが、日本語の古語、方言でもある。
黒部五郎岳、野口五郎岳などは、このゴーロが名前の由来となっている。
また、「ごうろ」がなまって「がわら」「かわら」になったものもある。
箱根の強羅(ごうら)、信州蓼科山の大河原峠などの語源でもある。
---------------------------------------------------------------------------
野口五郎岳って、、、
やっぱり人の名前が由来とかじゃなかったのね。。。
■金冷シ
コレも意外に色んな所にある地名だ。
---------------------------------------------------------------------------
通過するのに危険な場所を指す古語。
丹沢・塔ノ岳の直下にある金冷など、固有名詞になっているところも多い。
---------------------------------------------------------------------------
ナニが縮み上がるような、、、
そんな予想だったけど、、、ズバリ、、、かな。。。
■御室
南アの南御室小屋しか思い浮かばないが、、、
わりと意外な由来だった。
---------------------------------------------------------------------------
山小屋のうち信仰登山のためにできたもの。
---------------------------------------------------------------------------
今は一般の山小屋だが設立当初はそうだったのだろう。
山小屋と言うよりは宿坊に近い感じだったのかな??
■出合
南アの“角兵衛沢出合”や
瑞牆山の“天鳥川出合”など、よく聞く地名だ。
“二俣”との関係が面白い。
---------------------------------------------------------------------------
二つの川の合流する地点を言う。
本流に流れ込む沢が、水のない河原になっている場合に用いられる。
支流がやや大きい場合は合流点と言う。
沢と沢が合流するポイント。同じ場所を「二俣」ということもある。
下から見れば沢が2つに分かれるので「二俣」、
上から見れば、もう一つに沢に「出合う場所」である。
---------------------------------------------------------------------------
あとは私にあまり馴染みのない地名なのだが、
有名ではあるので載せておく。
■船窪、舟窪
---------------------------------------------------------------------------
山腹または山頂の舟底状の窪地。白馬岳の舟窪などの地名にもなっている。
船の底のような地形。2つの稜線が並んで走っている地形の間に見られる。
---------------------------------------------------------------------------
■廊下
---------------------------------------------------------------------------
垂直に近い岩壁の間を流れていく渓谷。
元は信州の人が黒部川に入って「ろうか」と言い出したもの。
黒部川ほど雄大でなくても廊下と言うこともある。
---------------------------------------------------------------------------
こうしてみると、、、
古語、訛ったもの、地形の状態など、色んな由来があって面白い。
なによりも、、、
地名で地形を想像できるってことが楽しいかな。
Posted by 工場長 at 13:59│Comments(6)
│山っぽい話
この記事へのコメント
うーん、なるほど、
まだまだ色々ありそうですね。
丸は大菩薩南嶺にも多いですね。
大蔵高丸、本社ケ丸、などなど、、、
Y-chan
まだまだ色々ありそうですね。
丸は大菩薩南嶺にも多いですね。
大蔵高丸、本社ケ丸、などなど、、、
Y-chan
Posted by Y-chan at 2010年03月11日 18:10
ふむふむ、なかなかためになる講義・・・・ぢゃまいか。
金冷やしは胆冷やしがなまったものかと思っていたが・・・・
面白いので続きをお願いしま~す。
金冷やしは胆冷やしがなまったものかと思っていたが・・・・
面白いので続きをお願いしま~す。
Posted by 賢パパ at 2010年03月11日 18:30
at 2010年03月11日 18:30
 at 2010年03月11日 18:30
at 2010年03月11日 18:30人生はいつもキレットの底。
そう信じて生きているのは僕だけですかそうですか。
どうすればキレットから出られるのか、もがき続けているんです。
だれも上からロープ垂らしてくれないし。
じつは、以前、細い糸が降りてきたんですよ、僕の上に。
そいつに掴まってたら、後から来るやつが僕にしがみついてきたんで、
この野郎!と蹴り落としてやったら僕の糸までぷつんと切れて...
え? あれはお釈迦様が垂らしておられたんですか!
なるほど。僕は永遠にキレットの底からは出られないようですな。
そう信じて生きているのは僕だけですかそうですか。
どうすればキレットから出られるのか、もがき続けているんです。
だれも上からロープ垂らしてくれないし。
じつは、以前、細い糸が降りてきたんですよ、僕の上に。
そいつに掴まってたら、後から来るやつが僕にしがみついてきたんで、
この野郎!と蹴り落としてやったら僕の糸までぷつんと切れて...
え? あれはお釈迦様が垂らしておられたんですか!
なるほど。僕は永遠にキレットの底からは出られないようですな。
Posted by いまるぷ at 2010年03月11日 19:07
Y-chan。ちわっス!!
そうなんですよ。
まだ、色々と気になるのもあるんですけど、
いくら調べても出てこないんですよね。
>丸は大菩薩南嶺にも多いですね。
そうですね。
丹沢、道志、中央線沿線の山に結構多い気がしますね。
別の何かで読んだんですが、、、
渡来人の移り住んだ周辺で多いらしいので、、、
古代朝鮮語を起源とする説じゃないですかね~。
そうなんですよ。
まだ、色々と気になるのもあるんですけど、
いくら調べても出てこないんですよね。
>丸は大菩薩南嶺にも多いですね。
そうですね。
丹沢、道志、中央線沿線の山に結構多い気がしますね。
別の何かで読んだんですが、、、
渡来人の移り住んだ周辺で多いらしいので、、、
古代朝鮮語を起源とする説じゃないですかね~。
Posted by 工場長 at 2010年03月11日 21:40
at 2010年03月11日 21:40
 at 2010年03月11日 21:40
at 2010年03月11日 21:40賢パパ。ちわっス!!
>ふむふむ、なかなかためになる講義・・・・ぢゃまいか。
面白いっすよね。
なんだか古くからの山文化が垣間見れて。
>面白いので続きをお願いしま~す。
わ。。。軽く言うなぁ~。。。
何日も情報集めてコレですからねぇ。。。
柳田國男の本なんかに詳しく載っているらしいんですけど、、、
本を買うまでのアレでもなく、、、
web検索だけじゃこんなもんが限度ですわ。
続編はないかなぁ。。。
>ふむふむ、なかなかためになる講義・・・・ぢゃまいか。
面白いっすよね。
なんだか古くからの山文化が垣間見れて。
>面白いので続きをお願いしま~す。
わ。。。軽く言うなぁ~。。。
何日も情報集めてコレですからねぇ。。。
柳田國男の本なんかに詳しく載っているらしいんですけど、、、
本を買うまでのアレでもなく、、、
web検索だけじゃこんなもんが限度ですわ。
続編はないかなぁ。。。
Posted by 工場長 at 2010年03月11日 21:49
at 2010年03月11日 21:49
 at 2010年03月11日 21:49
at 2010年03月11日 21:49睨下。ちわっス!!
む。睨下のバヤイはキレットの底ですか。
ワタクシは永遠に続くガスの黒戸尾根、、、です。。。
登っても登っても、やっぱり登りが続き、、、
そしてガスなので先も上も見えず、、、
たま~になだらかになったと思っても一瞬で、、、
アレ??下ってるじゃん、、、終わり??
と思ったら登り返しやがって、、、
ああ、、、ドコまで登れば、、、終わりがっ!!
そんでもって途中に小屋がありましてね。
休んで行けと言うんですよ。
小屋番さんが酒を持って。
つい飲んで寝てしまうとですね。
起きた所はソコは竹宇の駐車場だったりして。。。
なるほど。俺もず~っと登り続けなくちゃですな。。。
む。睨下のバヤイはキレットの底ですか。
ワタクシは永遠に続くガスの黒戸尾根、、、です。。。
登っても登っても、やっぱり登りが続き、、、
そしてガスなので先も上も見えず、、、
たま~になだらかになったと思っても一瞬で、、、
アレ??下ってるじゃん、、、終わり??
と思ったら登り返しやがって、、、
ああ、、、ドコまで登れば、、、終わりがっ!!
そんでもって途中に小屋がありましてね。
休んで行けと言うんですよ。
小屋番さんが酒を持って。
つい飲んで寝てしまうとですね。
起きた所はソコは竹宇の駐車場だったりして。。。
なるほど。俺もず~っと登り続けなくちゃですな。。。
Posted by 工場長 at 2010年03月11日 21:58
at 2010年03月11日 21:58
 at 2010年03月11日 21:58
at 2010年03月11日 21:58※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。